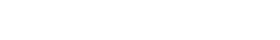こんばんは、サンクチュアリー本店の中村です。
昨年後半から現在にかけオーダーを頂きましたRCMが、かなりの
台数ありまして、どれも全て作業は進行はしており 少しずつ順番に
ご紹介して来ているんですけど、ここまでその内の半分も ブログで
お見せ出来ておらず、それぞれオーナーの皆さん「俺のまだかな~」
なんて、待っておられる事かと思います・・・
も~ 皆さんのお気持ち、充分わかってるんですけどね~!!!
私中村、ブログで進行状況をお見せして行くのは 日々大事な仕事と
わかってはいるんですけど、いかんせん、他にも毎日の見積もりや
工場でのメカニック業務、そして一応 社長業もこなしておりまして
ブログ 一辺倒という訳にも行かず・・・ (^^;)
毎晩自宅で 真夜中に下書きし、会社で仕上げてアップする・・・
最近 家族の目も、冷ややかになっておりまして・・・(苦笑)
そんな人生が何年も続いておりますので、今のペースがやっとな事
何卒ご理解頂ければと思います <(_ _)>
福岡県在住 T・Oさんの、RCM-515 MK‐Ⅱ(その1)です!
-thumb-437x291-68253.jpg)
ダミーエンジンを搭載し、レーザー測定とストレッチが完了した
フレームを これから加工して行きます。
何度もお伝えして来ましたが、フレームの補強で重要なポイントは
1 形状(形状は非常に重要。溶接する合口隙間が大きいのもダメ)
2 厚み(通常は 1.6mm、部分的に2mmも使用。厚いのはダメ)
3 材質(溶接での熱硬化が起こりやすい硬い金属、炭素鋼はさける)
4 治具(これ無しで溶接するのは不可能と言える程、重要なもの)
以上の4項目になります。
それら4つのポイントを、簡単にひとまとめでお見せ致しますね。
-thumb-437x327-68256.jpg)
まずは1の形状と2の厚み、そして3の材質から・・・
右に重なっているのが専用の押し型で、左にあるのが 型押しした
ガセットプレートなるもの。
板厚は 1.6mmのSS400と言う材質のプレートを用いており
型押しで この形状にめくり上げたものです。
めくり上げた事により、只の平プレートより何倍も捻じれ剛性が
上がりますから、1.6mmと言う薄い材料でも 非常に高い剛性の
補強材になる訳なんです。
-thumb-437x291-68259.jpg)
溶接する部位に合わせて 形をすり合わせ・・・
ここで隙間を造るのは 絶対にNGです!
溶接と言うのは、溶接後に金属が冷えてく工程で収縮が起こります。
その収縮により溶接した部位が引っ張り合って、歪や変形の原因に
なるんですが、これが意外に伏兵で 決して軽視出来ないもの。
サンクチュアリーのフレーム補強が その材料を一つひとつ手作業で
毎回造っているのは、そのフレームの個体差に合わせて 隙間のない
補強材を造りたいからであって、もちろん手間ひまは掛かりますが
とても意味のある 重要な事だったんです。
-thumb-437x291-68262.jpg)
擦り合わせが出来たガセットに穴を開け、そこにまた型押しの
専用工具をあてて 油圧プレスで押して行きます・・・
-thumb-437x291-68265.jpg)
押し切ると止まる構造になっており、最後まで押し切ると・・・
-thumb-437x291-68268.jpg)
穴のへりが めくり上がりました ♪
この加工は バーリングと呼ばれているものですが、めくり上がる
事で 只の穴が開いてる状態から 何倍も捻じれ剛性が上がります。
逆に言えば ただ穴が開いてるだけの状態と言うのは、むしろ剛性が
低下してる状態ですから、バーリングを施さないなら穴が開いてない
位の方が いいんです。
-thumb-437x291-68271.jpg)
フレーム補強用の材料が 全て出来上がりました。
今回は ダウンチューブが最初から二重管構造になってるMK‐Ⅱに
ステージⅡの補強を行うメニュー・・・
これがZ1ですと、もう4ヵ所ほど補強材が必要になります。
ちなみにパイプはSTKM13Cのシームレス(繋ぎ目なし)材で
プレート類はSS400材から切り出し、加工したもの・・・
サンクチュアリーでは 頻繁なクラックチェックが必要になる傾向の
クロモリ鋼を なるべく使用しない様にしています。
ノーマルフレームが普通の鉄である事から 補強材も近い性質の相性で
合わせており、STKM13CもSS400も溶接後の定着性が良く
安全性を重視したいストリート車では お勧めの材質と言えるんです。
-thumb-437x291-68274.jpg)
続きまして 4の治具のお話をしましょう。
ダウンチューブを左右繋ぐ補強パイプの下に、治具を組み合わせて
いるのが わかりますか?
エンジンハンガーのプレートと ジュラルミンの六角棒で固定する
治具で、ダウンチューブ左右の幅をキープさせる治具です。
-thumb-437x291-68277.jpg)
クランクケースのエンジンマウント部、その幅 262mmに 262mm
ピッタリの治具をガッチリ固定・・・
ピッタリの治具で溶接したら、冷間後に収縮して縮むのでは? と
思うでしょうが、補強パイプをダウンチューブの間に 若干強めに
打ち込み テンション効いた状態で溶接すれば、冷間後収縮しても
治具の寸法通りに仕上がりますので、この治具の存在なしで補強を
行うのは まず不可能と言えるものなんです。
ちなみに治具なしで補強しますと、ほぼ100% ダウンチューブの
幅が狂って エンジンを搭載した時に「アッ!」Σ( ̄□ ̄|||) てな
事になります(苦笑)
-thumb-437x291-68280.jpg)
この左右幅をキープする治具は、スイングアームピボット部にも
かませて溶接しています。
また おなじみリアサスレイダウンの治具も、あれが無いときちんと
正確に出来ない事は もうご承知な事でしょう・・・
だいぶ内容を はしょりましたが、このフレーム加工のノウハウは
月刊ヘリテイジ&レジェンズ誌にて 自分のコラムページでも より
詳しく書いておりますので、ご興味ある方は見て下さいね! (^^)/
-thumb-437x291-68283.jpg)
少々遡りますが、T・Oさんから 博多のお菓子を頂きました・・・
T・Oさん、ありがとうございます~ ♪
このRCM-515 MK‐Ⅱ・・・
なかなか凄い仕様のマシンになりそうなので、乞うご期待! (^^)