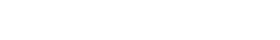覚悟は決まった・・・
脆弱な空冷エンジンで、屈強な水冷エンジンに抗う覚悟だ。
そしてそれが、如何に困難で険しい事かは 十分承知している。
むしろ・・・ 成し得る事が出来たとしたら、奇跡だ。
ゼッケン39 最後の挑戦 (その6)
画像25枚の大増版にて お伝え致します。

17インチホイール専用のジオメトリを持つ A16のフレームが
必要なのはもちろん、対等に戦う為には やはりエンジンが重要で
怒涛のトルク&ハイパワーが絶対に不可欠である・・・
-thumb-437x291-63404.jpg)
排気量のアドバンテージは大きく、今回 φ77のピストンを採用。
欠かす事のできない圧縮比は 12:1のトップボリューム設計で
ヴォスナーイタリア支社に直接依頼して ドイツ本社工場で製作した
オリジナル鍛造ピストンKITに、WPC処理を施したものだ。
-thumb-437x327-63410.jpg)
φ77ピストンを使うとなれば シリンダー側にも課題が出る・・・
スリーブの肉厚を最低限確保する事が シリンダーのライフに直結
するから、2.5mm以上の厚みを求めたいのだが、そうなると
φ77+(2.5×2)=φ82が 最低限の外径ラインとなる・・・
だがこれを空冷Zのシリンダーで施工すると スリーブ圧入部の肉厚に
問題があり穴が開き出すから、ブロック本体強度が低下してしまう。
-thumb-437x327-63413.jpg)
そこで選択したのが Z1000J/R系のシリンダーブロックだ。
実際には空冷GPz1100のブロックを使う事になったのだが
後期型シリンダーには若干の余裕が持たされており、φ82以上の
大径スリーブにしても ブロック本体に穴が開く事はない・・・
Z-1やKZ1000のシリンダーで ペラペラに薄くなってしまう
脆さは レースでは命取りなだけに、後期型シリンダーを使う判断に
迷いはなかった。
-thumb-437x291-63458.jpg)
問題は 腰下クランクケースがKZ系で、腰上がZ1000J/R系に
なると言う点である。
実は 似ていて異なる、2つのZ系エンジン・・・
クランクケースとシリンダー下面の形状が異なる為、必要になる
部分に溶接で肉盛りを施し、形を成型して行った。
-thumb-437x291-63461.jpg)
最終的にケース上面を面研して J系シリンダー下面の形状に。
手前の部分、少し色が異なる所が 今回溶接で肉盛りをした部分だ。
-thumb-437x291-63419.jpg)
Z1000J/R系 シリンダーを使うとなると、カムチェーンが
ローラータイプから ハイボチェーンになる為、KZ系で使用する
アイドラーは使用できなくなる・・・
クランクシャフトは GPz1100のものを使用する予定だったから
ハイボチェーンがそのまま使用できるが、シリンダーに取り付ける
J/R系のチェーンスライダーをクランクケースの上部へ固定できる
構造へと 改造しなければならない・・・
-thumb-437x291-63422.jpg)
そこでリアのチェーンスライダーを ケースにセットできる様にと
ジュラルミン無垢材をフライス盤で加工し 製作する事にした・・・
実はこの手法、今から15年以上も昔・・・
2004年の筑波TOFで 旧Zレーサー1号機のエンジンに採用して
いた技法であって、始めて試みるものではない。
ハイボチェーン化によるレスポンスが魅力で、現サンクチュアリー
コウガ店の立入が 中心となってトライしたもの・・・
当時 ハイボチェーンエンジンで見事、クラス優勝を果たしている。
-thumb-437x291-63425.jpg)
まさかあのエンジンを もう一度造るとは、思いもしなかった事。
KZのクランクケースに そのままピタッと収納できて、ガタつく
事などないブラケットを造るのだが、最後は結局 手作業で形状を
擦り合わせて行く・・・
目で見たままに、削り合わせて行くと言ったアナログな加工だが
カッチリした精度に仕上げてみせる。
-thumb-437x291-63428.jpg)
ジュラルミンのブラケットが出来上がったら 専用寸法のピンも
SS400材から削り出し、ピンの強度にジュラルミンが負けて
減らない様、同じくSS400のプレートを切り出し 曲げ込んで
ブレースアングルも造った・・・
-thumb-437x291-63431.jpg)
カムチェーンスライダーと組み合わせて、こうなるが。
ピン挿入穴が それぞれビシビシの位置関係にあるから、ピンを
入れて組み立てれば 全くガタ付かない精度に仕上がっている。
-thumb-437x291-63434.jpg)
あとはこれを、KZ系クランクケースに差し込むだけ・・・
-thumb-437x291-63437.jpg)
ピタッとはまって クランクケース上面と同じツラになる様、面を
出すのが最後に大変だったが、シリンダーブロックを載せれば
全く動く事のない J/R系チェーンスライダーブラケットである。
かつて造られた このKZのハイボチェーン仕様エンジンは、以前は
ハイレスポンスを目的としたものであったが、今回はビッグボアに
した際の耐久マージン対策であって、目的は異なる・・・
だが対策したとは言え、それでも高温・高負荷な状況にさらされる
エンジンである事に変わりはないから まだまだ余念は許されない。
そして・・・

3号機はもう一つ、フューエルインジェクションを採用する。
元々RCM USA A16がインジェクション標準装備だから
別段 違和感はない・・・
3号機に採用するスロットルボディは 大径 φ43のZX-10Rの
純正品で、試みるのはスロットルボディをダイレクトに取り付ける
構造にする事。
-thumb-437x291-63446.jpg)
GPz1100ヘッドのインテークポートは KZ系のポートより
最初から大きい設定だが、それでも φ43のスロットルボディを
取り付けるとなると直径の違いはあきらかで コブラポート形状に
なってしまうから、せっかくの大径ボディ効果も半減してしまう。
最新SSマシンのインシュレーターを用いて スロットルボディを
ヘッドにダイレクトに取り付けし、吸気ポートの口径を合わせて
混合気をスムーズに燃焼室へ送り込む形状にする事が課題である。
-thumb-437x291-63455.jpg)
やり方は実に アクロバティック。
歪まない様、細心の注意を払いながら 溶接で肉盛りを施し・・・
-thumb-437x291-63449.jpg)
インシュレーター取り付け部の面研は ノーマルの角度ではなく
わずかに傾斜を変え、ダウンドラフト効果をミックスしたものに。
全てキャド上にて算出し 検証した位置&角度だ。
寸法が異なるパーツ同士を ひとまず取り付けすると言うものでは
なく、専用設計で大径スロットルボディが取り付けられている事。
この構造こそが、常に思い描いていたイメージであった。
-thumb-437x291-63467.jpg)
穴径や位置も、キャドで算出した画像を1/1でプリントし
角度計で直角と水平を0に合わせ ネジ穴を開けて行く・・・
-thumb-437x291-63464.jpg)
ここからは ひたすらリューターで削るだけ!
ビッグバルブやハイカムと言ったレーシングパーツ達が、いかに
ハイスペックであったとしても、吸排気の通路たる このポートが
マッチングした容量に達していなければ、まるでバッフルがついた
マフラーの如き 性能になるから、ポートの径と形状は予想以上に
重要であると考えている。
-thumb-437x291-63470.jpg)
外見は性能に直結しないが、不要部分を残しておくのも意味が
ない事だし、最低限 それなりの形へと成形した。
-thumb-437x291-63473.jpg)
これが まだ粗削り状態ではあるが、吸気ポートの概要・・・
ヘッドが逆さまになっているので 実際には下側が上面である。
上にある小さなRは スロットルインジェクターの噴射軌道で
インシュレーターも同様の形状になっており、全く同じ形状に。
定石通り、バルブガイドに向かっていく部分を境に 右と左を
分ける形でリブを立て、吸気が渦を巻きながら流入して行く
スワール効果に期待した・・・
-thumb-437x291-63476.jpg)
仕上げは研磨部門 菊地の手で、鏡面&半鏡面に・・・
シェイクダウンまで時間が迫って来ている事もあり、無理言って
一日仕事でやって貰う。
-thumb-437x291-63479.jpg)
時間の関係上 外周ラインこそ少々イビツだが、内側は完璧に
段差なく、また エアーファンエルから入った吸気は 絞ぼられた
通路を通る事なく、ストレスフリーで流れる構造になっている。
この後やっと、バルブガイド&シートリングの内燃機加工へ・・・
だが・・・
加工が完了した燃焼室容積を測って わかったのだが、狙っていた
圧縮比12:1を 大きく切っている事が判明・・・
-thumb-437x291-63482.jpg)
スペック通りに圧縮が稼げない事は 往々にしてあるのだろうが
過剰なヘッド面研で圧縮を稼ぐのは できれば避けたい・・・
シリンダーブロック下面を 0.5mmスライスするだけで十分だが
そうなるとライナーを抜く事になるから、今となってはダメ・・・
次回、ケース上面をさらう事で 狙った圧縮化を図る事になったが
更に追い打ちで・・・
-thumb-437x291-63485.jpg)
期待のこのカムが 予定していたバルブスプリングでは線間密着して
しまう事が判明し、今回は見送る事に・・・
レース本番のエンジンでないとは言え、シェイクダウンでのパワーは
残念ながら 予想を大きく下回ったものになってしまうだろう。
この辺の話は また改めてご紹介します。